ラバ・シネマ
- みうらさここ

- 2023年9月10日
- 読了時間: 19分
1.春・金曜午後8時、羽根川シネマにて
『久しぶりー!サチ』
ふいに、高校の時の同級生からメッセージが送られてきたのは、春先の暖かくなってきたころだった。
文字の後ろに、ぽむぽむとしたかわいらしい動物の画像がついている。
小鳥遊さちは、ぐい、と炭酸水の入ったグラスをあおりながら懐かしいその名前を眺めた。
安藤まつり。
比較的閉鎖的だった女子校時代にも他の高校の男子と付き合っているという噂がたっていた彼女。
ひときわ目を引く綺麗な黒髪に、白い肌。
黙っていたら深窓の令嬢のよう。
見るたびに違う男を連れて歩いていることを知っていた私は、なんとも言えない気持ちで憧れの目を向ける同級生や後輩たちを見ていたわけだが。
そんなまつりが、今更なんの用だろうか。
ひととおり考えても答えは出ず、直接尋ねることにした。
『久しぶり。どした?』
グラスを置く間もなく、返信が来る。
『今、仲間とレイトショー見に行くのにはまっててさー!サチもどう?映画、好きだったよねぇ』
たしかに、映画は好きだ。
自分の唯一の趣味は、映画鑑賞。
学生時代にアルバイトを初めてから、毎週末欠かさず映画館に通っている。
だが。
グラスを座卓に置き、こめかみに指をあてる。
「ひとりなら、なぁ」
あいにく映画は一人で楽しむのが好きな人種だ。
高校の時友達と一緒に行ったこともあるが、作品に没頭することができなかった。
その場は笑顔で収めたものの、「次からは一人で行こう」と心に誓っていた。
そんな私が。
複数人で。
映画。
「断るか」
文字を入力しようとしたとき、ちょうど受信を告げる通知音が鳴る。
『じゃあ、明日午後8時に羽根川シネマに集合ねぇ』
私は、携帯をベッドに放り投げた。
そうだ。
安藤まつりはこういう奴だった。
「…しょうがない」
行くしかないのだろう。
というか、有無を言わせず、「来ないと許さない」というオーラを返信タイミングと文面から感じた。
別に、誰かと映画を見ることが嫌なわけではないのだ。
物語に没頭できないことが。
作品の空気を吸って、そのままの気持ちで帰れないことが。
ただただ、惜しい。
「あ!サチー」
にっこりと笑って、まつりがこちらに手を振る。
近くにいた男子高校生の視線がまつりにくぎ付けになるのを横目に、ひらひらと手を振り返す。
「相変わらず百発百中だな」
「私のせいじゃないもん。私が可愛く生まれてきたせいだもん」
それはそう。
「で、この人!今カレ!」
腕をひっぱられ、ふんわりとした髪に優しい目元の男性が「どうも」と声をかけてきた。
さきほどの男子高校生は、ため息をついて駅の改札に向かっている。
あきらめろ。こいつは人の言うこと聞くような奴じゃないんだから。
「よろしく。今度はゆるふわ系か」
「ちょっと!『今度は』とか言わないでよ。今度こそ、運命の人なんだから」
「まつりも『今度こそ』って自分で言っちゃってるじゃん」
「いいもん。今まで付き合ってきた人のこと全部話したし、オッケーもらってるんだもん」
そりゃ優しい人捕まえたな。
でも、たしかに。
「まつりが可愛いのは、まつりのせいじゃないよ」
そう言うと、まつりはふわりと笑った。
「サチのそういうところが好き」
私はこそっと新しい彼氏さんに耳打ちする。
「ちょっと彼氏さん、もう浮気し始めてますけど」
「ちょっと待って!浮気じゃない!浮気じゃないもん!」
「地獄耳だな」
ぷぅ、と頬をふくらませるまつりを見て、ふはっと吹き出す。
「で。メンツはこの三人?」
「違う違う、もっと来るよー」
そのあと集まったのは、5人の若者たち。
全員、男。
ちょっと待て。
私はまつりの肩をがっと掴んで小声になる。
「おい、これどんな集まりだよ」
なにを聞いているのか、とでも言いたげにまつりはキョトンとした顔をこちらに向ける。
「まつりの元カレ達」
こ い つ 。
「へぇ、たけしさんってIT系なんですかー?僕もプログラミングの大会で一応賞取っててー」
「え、そうなんだー俺大学の時スポーツ大会全国で1位だったなー」
「俺美容師なんだけどー、その髪型変えた方がいいよー輪郭と合ってない」
なんかあっちの方で男のどろっどろのマウント合戦始まってるんだけど。
すでに空気が泥沼なんだけど。
こほん。
咳払いをして、まつりに向き直る。
「私が呼ばれた理由は?」
「いや、サチのことだからまだ一人なんじゃないかなーって。まつりと別れたけどぉ、上玉の人たち集めたから、誰でも持ってっていいよ?」
なんだその中古の服のバーゲンセールみたいな企画は。
全員まつりとの復縁目当てだろ。
「「きついな…」」
誰にも聞こえないように呟くと、隣にいた男も同じ言葉を口にしていた。
一見軽い雰囲気なのに、その声は落ち着いている。
そんな、男。
私はその男に話しかけることにした。
この中では一番話が通じそうだ。
「あなたはまつりの元カレじゃないの?」
「ただの一般人。これといった特技もないよ」
救世主がここにいた。
あまりこう、まつり周辺の男どもとも拗れていない気配を感じる。
そこらへん、というか。
人とぶつからないようにうまくやっているんだろう。
「どういうつながり?」
「高校の時、塾でノートを見せていたというか、見せるよう脅迫されてたかな」
何やってんだあいつ。
「あんたは、なに?」
初対面にあんた呼ばわりかよ。
私は内心ため息をつきながら名乗った。
「さち。ただの高校の同級生」
へえ、と男は意外そうな声をあげた。
「ただの同級生にしては、あの子がずいぶん心を開いているように見えるけど」
「気のせい気のせい。ほら、マウントボーイズが動き出したよ。行こう」
まつりは、可愛い。
たぶん幼い頃から、ずっと可愛い。
可愛いから、愛される。
いろんな形で与えられるそれに、疲れてしまうこともある。
少し拗れた形の孤独を抱えていたりもする。
目の前にある愛がわからなくなったりもする。
ちらりと、横を歩く男を流し見る。
この男は、人の心の形が直感でわかるタイプの奴なんだろう。
嫌な目を持っている奴だ。
いや、良い目を持っているのか。
同族嫌悪。
あまり弱みを見せたくないタイプの奴だ。
「たぶん、私は君のことが嫌い」
その男に言い残して、飲み物を買いに行く。
どうせ今日だけの付き合いなのだ。
無理して友好的にふるまう理由もないだろう。
戻ってきて、コーラを差し出す。
男は携帯から顔を上げ、そのまま首をかしげる。
「?」
「君の分」
「うん?」
「だから、君の分だって」
その男は、目を見開いたあとに、あっはっはっ、と声を上げて笑い出した。
「なに?なんか変なもの食べた?」
「いや、小鳥遊さん、嫌いって言った相手に、飲み物買ってくるから…ふっ」
笑いはなかなか収まらないらしく、男はぷるぷると震えている。
自分に飲み物を買った人間を笑うなんて、失礼なやつだ。
だが、この男。
なんだか面白い。
「名前教えてよ」
相手の笑いが収まるのを待ってから、しずくのついたコーラを差し出す。
男は受け取って、自分の名前を言った。
「一ノ瀬。下の名前は個人情報だから秘密で」
「私だけ情報過多で不利だな」
「人間関係の捉え方は有利不利だけじゃないでしょ」
「そりゃそう」
私がにやりと笑うと、一ノ瀬もにやっと笑った。
午後8時、レイトショーにて。
私は久々に、面白い人間に会った。
2.夏・三十七と五分の夜
レイトショーの会は、事実上あの1日で解散した。
主な理由は、まつりが飽きたからだ。
あの子はあの子で、この世を楽しむ手段を探しているんだろう。
出会った時からまつりはいつでも表情豊かだが、あの子の心が満たされている瞬間はなかなか見たことがない。
解散後、なんとなく同じ時間にレイトショーに行くと。
「あ」
「お」
一ノ瀬がコーラを持って待っていた。
2つ。
「…そんなに好き?コーラ」
一ノ瀬は、ふはっと笑った。
「それ、わかってて言ってるでしょ。はい」
差し出されるコーラを、手に取る。
しばらく待っていたのか、外には水滴がつていた。
「びたびたじゃん」
「それを言うならびしょびしょでしょ」
「男がそれ言うとなんかやだ」
「なにそれ。神経質女」
「秘密主義男」
ふはっと、笑いあう。
それから、なんとなく金曜の夜は羽根川シネマに足が向いている。
コーラは先についた方がおごることになんとなくなっていて、たぶん半々くらいでおごりあってるはずだ。
苗字以外なにも語らないこの男とすごすこの時間が、なんとなく気にいって。
それくらいの距離感じゃないと、また、何か壊れそうで。
壊しそうで。
そうこうしているうちに、蝉がわんわん鳴いている季節になった。
ただ、毎週金曜の夜にレイトショーを一緒に見る。
それだけの関係性。
それがどうしてこうなったのか。
今一ノ瀬は、私の来客用の布団で寝ている。
別に何もない。
何かが起こるはずもない。
ことの原因は、一ノ瀬にあった。
いつもと違う様子は、出会った瞬間に見て取れた。
いつものように待ち合わせ場所に向かうと、一ノ瀬は映画館の壁によっかかっていた。
顔が赤い。
「今日は帰りなよ」
出会ってそうそう、コーラを2つ持っている男に言い放つ。
「こわ。なんでわかるの」
「自動人心把握機に言われたくない。帰れ」
「いやだ」
ずず、と鼻をすすりながらいつもより緩い動作でコーラを手渡してくる一ノ瀬にむかついて、私は気づくとその袖をひっぱっていた。
羽根川シネマから徒歩十分。
どこにでもあるようなアパートの2階。
そこに、私の部屋がある。
手早く来客用の布団をひく。
「ちょっといろいろ買ってくるから寝てて」
「1日着てた服で布団入るの…悪いって」
これ以上私を苛つかせるのかこの男は。
ふらふら動く一ノ瀬に掛け布団を投げつけて敷布団の上に吹っ飛ばしたあと、鍵と財布を握って近くのスーパーに向かった。
スポーツドリンクに、レトルトのおかゆ。ゼリー飲料。
あ、やば。買い物袋忘れた。
小さくため息をつく。
「手で持って帰ればいいか…」
「ただいま」
布団の中で横になっていた一ノ瀬は、はっとしたようにこちらを見た。
「なに。ただの挨拶」
「あ、ああ。おかえり」
そのまま、もぞもぞと起き上がる。
手早くおかゆをあたため、ゼリー飲料とスポーツドリンクと一緒にトレイにのせて一ノ瀬の前に置く。
一ノ瀬は顔の前に片手をあげて私を拝んだ。
両手を動かすのも厳しいのだろう。
「正直、まじで今日の仕事の記憶ないくらいやばかった。ごめん。助かった」
「死ななきゃいい」
目の前で誰かが死ななきゃなんでもいい。
一ノ瀬はなんとも言えない顔で私を見た後、ゆっくりとおかゆを口に運んだ。
「なんていうか、助けられてる俺が言うのもなんだけどさ」
「あ、まって」
「?」
「なんか見えても、見えないふりをしていてよ」
目がいい人だということは、なんとなく察しがついていた。
視力の問題ではない。
人の心や形を見る目のことだ。
だから、あんまり深入りせず。
深入りさせないように、気をつけて行動していた。
「わかった。じゃあ一般目線コースで」
「?」
「弱ってても男を簡単に家にあげない方がいいよ」
はあ?
私は首をかくっと傾けた。
「一ノ瀬が自己管理できてないのが悪い。赤い顔してふらふらしてたくせに」
「ただの風邪を致命傷みたいに言うじゃん」
気づくと一ノ瀬は、真剣な顔でこちらを見ていた。
「…」
その瞳は、どこまでも透明で。
まるで、鏡のようだ。
見たくないものまで、見えるような。
まぶたの裏に蘇る、記憶。
スローモーションのように、地面から離れて空に浮かぶように。
嬉しそうに。
やっと楽になれると、喜ぶように。
落ちていった。
その姿を、雲間から差し込んだ光が照らしていた。
まるで、彼女を祝福しているみたいだった。
まるで映画の美しいワンシーンのようなそれに、頭が追い付かないまま。
私はただ身を乗り出して、見ていた。
でも、地面に落ちる前の一瞬。
その顔がこわばるのを見た。
あの子は自由になりたかっただけで。
死にたいわけじゃなかった。
あたりまえだ。
ただ、辛かったのだ。
人生が。
生きることが。
見出せなかったのだ。
生きることの、意味を。
「最悪」
ゼリー飲料を一ノ瀬に投げつけて、私は布団を横に敷いた。
「お風呂入ったら?」
「いい」
今日はもう、何かもどうだっていい。
一ノ瀬は何か言いたげだった。
私は、静かに布団の中にもぐりこんた。
翌朝、一ノ瀬の熱をはかった。
36度5分。
平熱だ。
「俺より、君の方が重症なんじゃない」
きっと風邪や体調のことではないのだろうが、さらりと気づいていないふりをする。
「風邪ひくやつに言われたくない」
「風邪は誰でもひくけど、小鳥遊の持ってるそれは小鳥遊だけが背負ってるものでしょ」
それは、そうだろうけれど。
誰でもひとつやふたつ持ってるものだろう。
面倒見がいいと、言われていた。
高校。
大学。
職場。
その根っこに、あの光景があることを。
知っている人は、いない。
なぜなら、私はあのあと、逃げたからだ。
その光景から。
現実から。
一緒に笑った記憶から。
下からあがった悲鳴に。
広がる赤色に。
背を向けて。
屋上から階段を駆け下りた。
水道の蛇口をひねって、頭をその水に浸す。
頭。
腕。
手。
どれだけ体を水で流したって、あの顔は頭から離れなかった。
どれだけ逃れようと、それは事実として、そこにあった。
清水仄香は、高校三年の夏、学校の屋上から飛び降り自殺をした。
学校中にその言葉が飛び回るように充満していくのを感じた。
ただ、飛び降り自殺というその言葉に私はいささか違和感を覚えた。
彼女は、それはそれは嬉しそうに、飛んだのだ。
それは、落ちたというより浮き上がるような。
飛び降りるというよりは、飛び立つような。
そんな光景だった。
着地の間際までは。
じっとりとかいた汗を、誰にも気づかれないように腕でぬぐう。
喜んで逃げたい奴はいても、
喜んで死にたい奴はいなかった。
3.秋・こっくり情報戦
「今日の、どう思う」
炭酸水の向こうで一ノ瀬が言う。
私はグラスを揺らして、泡が一斉に水面に向かうのを見ていた。
綺麗な動きだ。
「どこに関して」
私は片眉を上げた。
ふは、と一ノ瀬が笑う。
「テーマ絞る?細かいね」
一ノ瀬が熱を出して泊っていったあの日から、レイトショーが終わると私の家で感想やら言葉遊びやらをすることになった。
しかし私は一ノ瀬を家にあげつつ生活時間を合わせるつもりはなく、
「お風呂入ってくる」
と普通に言う。
そのたびに一ノ瀬は一瞬間をおいて、
「いってらっしゃい」
とゆるゆると手を振る。
どうやら一ノ瀬の恋愛対象は女性で、ストレートらしい。
風呂に入る発言をした後、一ノ瀬のその微妙な間を感じ取った瞬間、私は苦虫をかみつぶした顔になる。
男に生まれればよかった。
こいつの隣で肩を並べていたいのであって、こいつの前で女になりたいわけじゃない。
ある日、一ノ瀬がゆらりと手をあげた。
「ちなみに、俺が小鳥遊の後に風呂入るのはアリ?」
「普通にアリ」
どうやら、レイトショーの後に我が家に寄ってから帰宅して風呂を沸かすのが面倒らしい。
わかる。
「ただ、ボディソープとシャンプーリンス使用代として何かよこしなさい」
「もちろん。これどう?」
一ノ瀬はごそごそと荷物から小瓶を出した。
「富士山麓の水を使った炭酸水」
「風呂でも布団でも自由に使え」
即答した。
そりゃ、こんなものを出されたら即答するしかない。
人の心の形を見通す男は、人の好みを把握するのも早いらしかった。
私はそこは自信をもって鈍いと言える部分なので、尊敬するばかりである。
風呂からあがってきた一ノ瀬は、来客用の座椅子に腰掛けた。
勝手知ったる他人の家、である。
さっそく、いただいた炭酸水をグラスに注ぐ。
ドロップ型のグラスに炭酸水を注いで、泡が綺麗に上に上がっていくのを見るこの時間が好きだ。
その様は、美しく儚い。
そういえば。
「一ノ瀬は私の好きなものを把握しているけど、私は一ノ瀬の好きなものを知らない。不公平だ」
最初に出会った時から下の名前を言わないこともそうだが、一ノ瀬は自分の情報を開示しない。
今となってはどうでもいいのだが、なんとなく気になるところではある。
「まずくない食べ物、苦手じゃないデザインの服、殺伐としていない空間、気が合わないわけではない人間」
なるほど。
嫌悪回避型の人生観か。
「小鳥遊は苦手じゃないし気を使わないし一緒にいて楽。かな」
へえ。
つまり私は一ノ瀬のブラックゾーン、アウトポイントを回避できている人間というわけか。
「それは喜べばいいのか、安心したらいいのか、不思議な心持ちになったらいいのか、今後の付き合い方に緊張感を覚えればいいのかよくわからなくなる返答だな」
「小鳥遊はそのままでいいよ」
変わらないでいてくれたらそれでいいよ。
一ノ瀬は、つぶやくようにそう言って、その日はそのまま帰った。
変わらないことには定評がある。
化粧をする年齢になった世の女子へのお決まりの「綺麗になったねぇ」という言葉はいただいたものの、
「変わらないね」
「落ち着く」
「また会おうね」
「本当、小鳥遊って小鳥遊よな」
同級生や古くからの友人からの定評はこれである。
「なんで変わらない方がいいの」
レイトショー帰り、夜に食べる菓子を買いに行ったスーパーで一ノ瀬に聞いてみた。
ちなみに二人とも酒は飲まない。
私は飲めないのだが、一ノ瀬は飲めないのか飲まないのかわからない。
わからないことばかりだ。
「小鳥遊が抱えてるものを教えてくれたら、教えてあげてもいいよ」
一ノ瀬は私の顔を覗き込んで、そう言った。
「またそういう…下の名前といい、私の方が圧倒的に情報漏洩してるじゃないか。お前、本当に気に食わん」
「あっはっはっはっは」
つぼにはまったように腹を抱えて笑う男と、それを見ながら苦い顔をする女。
傍から見たら温度差のあるカップルのように見られるのだろうが、この二人には恋人特有の空気は微塵もない。
スキンシップもない。
性行為もない。
それが、こんなにも心地いい。
本当にちょうどいい距離感だ。
少なくとも、私にとっては。
おそらくは、一ノ瀬にとっても。
「…前に好きな人がいてさ」
一ノ瀬が、ぽつりと話しだす。
「本当に好きだった。でも、何年かして再会したら」
俺の好きなところ全部なくなってた。
面白さも。
味わい深さも。
楽しさも。
軽やかさもない。
「そんな人になっちゃってたからさ、俺それから人を好きになるのが面倒になっちゃって」
面倒っていうか、怖いんだろうね。
ふふ、と一ノ瀬は炭酸水とチータラが入ったレジ籠をくるりと回す。
私は、思わずそのどこかに行ってしまいそうな手を掴んだ。
一ノ瀬の目が、見開かれる。
「私は、変わらない」
というか、変われない。
「自信、あるぞ」
まっすぐに、そのガラスのように透き通った目を見る。
しばらく、そのガラス玉の奥にいろんな色がはじけたあと。
一ノ瀬は、やっぱり笑った。
「あっはっは!あー、おかしい。俺、こんなに面白い人と出会えるなんて思わなかった」
「お前の人間のツボがおかしいだけだろ」
それを聞いて、さらに一ノ瀬はぷるぷると震えながらお腹を抱えた。
失礼な奴め。
面倒くさいので、そのままレジ籠を奪っておいてレジに向かう。
「あっ、待って。これ」
一ノ瀬はせんべいの袋をレジに置かれた籠に入れた。
「しょっぱい系の煎餅と緑茶。俺の好きなもの。覚えといてよ」
へえ。
避けたい苦手なものじゃなく、好んで選ぶもの、ね。
はいはい、と適当に返事をしながら。
私は上機嫌で会計をした。
4.冬・こたつ論争
「みかん」
「せんべい」
「炭酸水」
「緑茶」
「平行線だな」
交互に提案しつつ着地点を模索している二人。
このたらたらとした会話の原因は一時間ほど前にさかのぼる。
「あーこたつ。いいねぇ」
家主よりも先にそこに入った男の名は一ノ瀬。
「上着は脱げよ」
はーい、と言いながらこちらに上着を手渡してくる一ノ瀬。
わしゃあんたの奴隷か。
「自分でやりな」
「先生、小鳥遊の心が狭いです」
「大人に先生はもういないの」
そう。
大人に先生はもういない。
だからこそ、親しい中にも礼儀ありということわざがあるのだ。
一ノ瀬はもぞもぞと動いていたが、結局上着を再び羽織った。
「もういいか、これで」
「おいおい」
「と言いつつ、小鳥遊も上着着たまま入ってるじゃん」
そりゃそうだ。
この外の寒さから帰ってきて優先順位が一番高いものといえば、『こたつの電源をつける』であり、二番目は『こたつに入る』だ。
「いいねぇ。俺ん家こたつないからさぁ」
「人生半分くらい損してるぞ」
「反論はできないねぇ」
はーあ、と二人でこたつを味わうこと十分。
机の上で視線を交わしあう。
先に口を開いたのは私だった。
「お茶は淹れなくていいのか」
「そっちこそ。いつもの炭酸水はいいの」
目が合ったまま、しばらく時間が流れた。
またしょうがなく、口を開く。
「この前買ったせんべいはいいのか」
「そっちこそ、ちーたらがあっちで待ってるよ」
また、しばらく時間が流れる。
これがあるから、こたつは怖い。
魔法にかかったように、そこから動けなくなるのだ。
その、あまりのぬくさに。
少しディベートをした結果、行動を絞ってジャンケンで負けた方がそれを行う、という形に落ち着いた。
つまり。
どちらも、一度入ったこたつから出たくないのだ。
「じゃーんけーん、」
「待った。まだ何をするか決めてない」
「え、緑茶淹れて炭酸水グラスに注いで、せんべいとちーたら持ってくるだけじゃん」
「時間見ろ。このくだらない戦いですでに一時間経過してる。どう考えても今必要なのは晩御飯だろ」
「え、今日食べてなかったの?」
「食べ損ねた」
「嘘。俺も今日食べ損ねてた」
うぐぐ、と二人で頭を抱える。
手間を取るか、腹を取るか。
「こういう時大切なのは、何を一番にするかだよね」
「何を一番に」
「水分にするかつまみにするか、食事作りにするか」
それであの、冒頭の会話に戻るのだ。
「みかん」
「せんべい」
「炭酸水」
「緑茶」
「鍋」
「よし。鍋にしよう」
しかし、動かない二人。
つん、とつま先で一ノ瀬をつつく。
「いつも場所貸してやってるんだから今日くらい作ってもいいじゃないか」
つん、とつま先でつつかれる。
「対価として炭酸水は納めているんだから小鳥遊が作ってもいいじゃない」
はぁ。
ため息をついて立ち上がったのは、二人同時だった。
顔を見合わせ、互いに目を見開く。
笑ったのは、やっぱり一ノ瀬だった。
「作ろうか。一緒に」
小鳥遊?
一ノ瀬に聞かれて、その笑顔に視線を奪われていたことに気づいた。
非常に。
大変不服である。
自分に対して。
変わらないと言ってあの手を取ったのはどこの誰だったのか。
なんとなく落ちつかず、ふい、と顔をそむける。
「ねえ、どうしたの」
「なんでもない」
「なんでもなくないでしょ?」
「な・ん・で・も・な・い」
一ノ瀬は私の顔を覗き込んだ。
そのまま、ガラスのような瞳を一度、二度瞬かせる。
瞳の奥に、また何かの感情がはじけるのを見る。
「別に、変わってもいいよ」
小鳥遊なら。
一ノ瀬はそう言いながら、冷蔵庫の野菜に手を伸ばした。
私はぐ、とその背中をにらみつける。
振り返った一ノ瀬は、「やっぱり小鳥遊は面白い人だねぇ」と、また笑った。
5.春・ひらめいて、春
あのこたつで鍋をつついた一夜から、どちらともなく食材を買って晩ご飯を一緒に作って食べるようになった。
「んで、上司がさ、そういう指示を出すわけ」
「はぁ?んで、どうしたんだ」
「だから、表向きは従うけど個人的な弱みは握っておくよね。とりあえず」
「お前本当に敵に回したくない奴だな」
あれだけ自分のことを話さなかった一ノ瀬が、日常の話を始めたのは桜が咲き始めたころだろうか。
花も盛りになった金曜の夜、一ノ瀬が「今日は花見をしよう」と言い出した。
私も、別に異論はなかった。
冷蔵庫の中身もちょうど空だったし。
映画を見終わった後、スーパーに寄って寿司と緑茶と炭酸水を買った後、近くの公園に行った。
さすがに、この時間ベンチには誰もいない。
「よかった。ここ、たまにカップルがいちゃついてんだよな」
「別に俺はしてもいいよ。そういうこと」
私の顔を見た一ノ瀬は腹をおさえて笑い出す。
「それ、今小鳥遊がどんな感情かすごい、もうっ、全面に、っふふ」
「お前思ってるのか思ってないのか微妙なラインのこと言うの特技なのかよ」
一緒に時間を過ごせばなんとなくわかってくる。
こいつの言葉は、そのままの意味の時と、相手の反応を試すための軽口の時がある。
非常に面倒な奴だ。
前に鍋作った時の言葉は、どちらかわからなかったけど。
「私には本音で話せ。大事な時にわからなくなるから」
「わかった、わかった」
涙をふきながら笑う一ノ瀬を見て心底殴りたくなった。
私はこんなにも「変わらない」努力をしているというのに。
勢いよく割り箸を割り、寿司を口に運ぶ。
そのまま、視線を街灯の近くの夜桜に向けた。
「美味しいね」
ぽつりと、一ノ瀬が言う。
「うん。うまい」
私もそう返すと、ガリをつまんだ。
「あれ、ガリ食べられる人?」
意外そうに尋ねられるが、生まれてこの方寿司を食べる時にガリを残した覚えはない。
「お前でもまだ知らないことはあるんだぞ」
少しぬるい風が、ほほをくすぐる。
「へぇ」
少し、ガラスの瞳のむこうに色が小さくはじける。
不満の色。
それが意外で、ガリをつまんだまま少し、私は固まった。
いや。
だって。
そもそも。
「…私はまだお前の下の名前も知らないじゃないか」
ぱちりと、ガラスの瞳が瞬いて。
一ノ瀬の顔に笑みが浮かんだ。
「…そうだね」
そして一ノ瀬はまっすぐにこちらを見ながら、こう言ったのだ。
「めぐる。一ノ瀬、めぐる。俺の名前」
どうか。
どうか、忘れないで。
そう告げた声は少し、揺れていた。
今きっと、一ノ瀬はなにかの壁を越えてくれたんだろう。
その手をそっと取って、微笑む。
「小鳥遊さちだ。これからもよろしくな、めぐる」
ガラスの瞳が見開かれる。
花の盛り、夜桜の元で。
私達はやっと、何かに。
なったのだろう。
なれたのだろう。
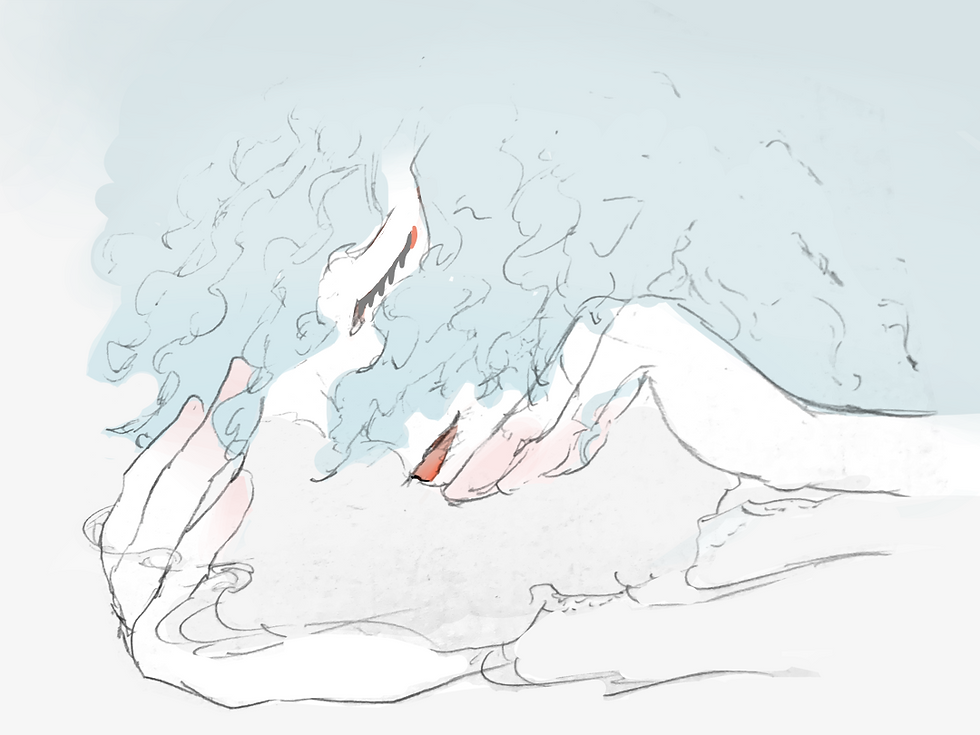
コメント